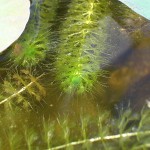この作品のジェームズ・ブラウン(チャドウィック・ボーズマン)は一筋縄ではいかない人物だった。ただ、その複雑さにはそれなりの理由があったり、目茶苦茶なようでいて実は理解できないほどではないことが、わかってくるような作りになっている。
例えば、バンドの仲間を裏切るような形で独立するは、独裁者のように意のままにリハーサルを取り仕切るはの所行の数々に耐えていた親友のボビー・バード(ネルサン・エリス)までもが、(思い遣りのないセリフに)ついに堪忍袋の緒を切らし(というか匙を投げて)、「お前は人との繋がりなんて必要ないんだろう。独りきりでやればいい。」と去って行く、その場面から、シアターでのコンサートが大成功した夜、生き別れの母(ヴィオラ・デイビス)と再会したときへとフラッシュ・バックして、母にお金を渡し、もう来るなと言いながら、内緒で経済的援助をするようにボビーに指示を出す。
あるいは、冒頭、理不尽な言いがかりでライフル銃を乱射した後どうなったか、忘れた頃(おしまいの方)に明かされる。息子ジュニアが亡くなり、薬をキメて・・・・冒頭シーンにカット・バック。その後、車で逃走し御用となったのであった。
それぞれのシーンに作り手が出した答えは、ジェームズ・ブラウンは「人との繋がりを大切にする」し、「息子を亡くした哀しみのあまり刑務所送りになった」ということのようだ。私が気づいたのはこの二つだけれど、時制を超えた場面と場面をパズルのようにつなげると万事このように、作り手の様々な答えが用意されているような気がする。
ジェームズ・ブラウンは、子どもの頃、貧しさのため親に捨てられたが、才能に絶対の自信を持ち、ギンギン・シャウトにキレッキレのステップと頭脳で抜け目なくしたたかにショービズ界を渡り、ステージではカリスマ、まさに破天荒を地でいった。恩人はマネージャーのベン・バード(ダン・エイクロイド)と親友のボビー・バードだった。そういう作品だったと思う。
ミスター・ブラウンと呼ばせるけれど、自分も相手をミスター付けで呼ぶところと、ライブシーン、よかったー!