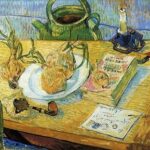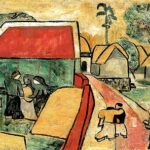どこにあるかは知らねども、行ってみたいと思っていた美術館。向こうからやって来てくれた(ほくほく)。
しかし、展示作品の2番目から暗雲が立ちこめる。焼き物と果物を描いた絵。もしかしたら剥いた皮も含めて陶器の果実だったのかもしれない(もやもや)。
風景画はやっぱりいいよね~と思いながら進む。しかし、女性のヌードでまたもや暗雲。とても綺麗、綺麗すぎるのでウソっぽい。デジタルの映画になって俳優のアップが見苦しくなった世の中ですぞ。ポーズや小物の配置などの作りすぎが、いつの時代だろうと思ってしまう。そして、ふと、写実の画家全員が本物ソックリに描いたら、そこに個性は表れるのだろうかなどと思う。
で、素晴らしいと思ったのが、五味文彦の作品。どれもいい。カメラ目線の「ひとみ」。右から見ても左から見ても、ずっとこちらを見ている。いるね!こんな人。静物画もパンもレモンも食べれそう。レースがレース。「ホワイト・スクエアー・コンポジション」、面白いねぇ!3個の透明な容器に入ったレモン、キャベツ、白菜。何なのこれって見入ってしまう。衝撃的なのが「ヒゲを愛した女」。さっきの「ひとみ」さん?幾重にも破かれている。さっきのひとみさんは「居た」のだが、今度は紙だからねぇ。でも、すごい存在感だ。「いにしえの王は語る」は森の中で古木に対峙しているような感じだ。
塩谷亮の少年を描いた「光韻」と着物の女性を描いた「相韻」も好きだ。モデルの個性が強い。写実といっても画家の個性はあるのだと実感。
島村信之「ニジイロクワガタ-メタリック-」「オオコノハムシ-擬態-」は、虫嫌いでも「ほしい」と思った。そして、同じ人が描いたとは思えない「籐寝椅子」は、「あるある、こんな時間」と思えた。白いカーテンに昼間の陽射し、寝椅子に横になっている女性。ポーズはとっていると思うが自然に感じられ、全体的に白っぽいのも穏やかな時間を感じさせられた。
人物では他に石黒賢一郎の作品群「綾○○○的な」「ア○○的な」「INJECTION DEVICE(3rd Lot)」「存在の在処」が、人物の個性が感じられてよかった。
展示室が変わって廣戸絵美「階段」が不思議でたまらず長く立ち止まってしまった。鑑賞者の立ち位置は踊り場で、左の階段を見下ろし、右の上り階段とそれに続く上階の廊下(床?)を見ているような絵なのだが、上り階段が急傾斜に見えてしかたがなかったのだ。実際にこんなに急な階段なのか、普段私たちが上っている普通の階段もよく見ると本当はこんなに傾斜しているのか。
大畑稔浩「剣山風景-キレンゲショウマ」のうっそうとした少し湿気がある感じが印象に残っている。同じ作者の「陸に上った舟」の乾いた空気と大違い。空気を描く画家なのかもしれない。
写実主義の画家といえば『マルメロの陽光』のアントニオ・ロペス。2、3年前に長崎で展覧会があって行きたかったが叶わなかった。今回の展覧会の主催が高知県立美術館であれば、美術館ホールで『マルメロの陽光』の上映会があっただろうか。
(2021/04/23 高知県立美術館 主催:RKC、高知放送、高知新聞社)