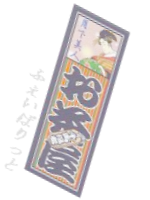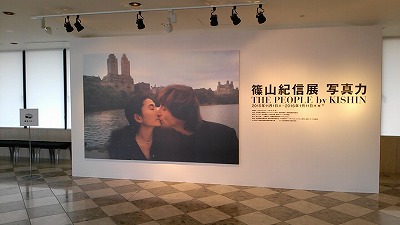いっしょにコンサートに行ったことがある友だちがメールで知らせてくれて、う~ん、やっぱりショックだった。
で、『オデッセイ』が公開間近であることだし、そこに使われているという「スターマン」が真っ先に思い浮かんだ。
youtubeで聴いていると、ああ、ボウイもスターマンになったんだなぁと思ったりした。
https://t.co/0TMDEm2zCJ
スターマン
— お茶屋 (@ochayacco) 2016, 1月 11
ボウイがツアーに復帰するなら私もそれに備えておかなくちゃというような話をしたばかりだったのに。もうライブはないのだなぁ。そう思うと、コンサートで必ず歌っていた「レベルレベル」を思い出す。乗りのいい曲というだけでなく、ボウイ自身も好きな歌だと(勝手に)思っている。やんちゃな歌詞がお気に入りなんじゃないかな。
https://t.co/KCkPYV8vYR
レベルレベル
— お茶屋 (@ochayacco) 2016, 1月 11
「ピンナップス」というカバーアルバムもよかったけれど、「ヤングアメリカン」のなかの「アクロスザユニバース」が強烈だった。ビートルズとは全然ちがう歌になっている。
https://t.co/ccIW1NBsHe
アクロスザユニバース
— お茶屋 (@ochayacco) 2016, 1月 11
そうか、ジョンに会えるね。ジョンに会えるならフレディにも会えるじゃん!
https://t.co/pxNQnYnnFu
アンダープレッシャー
— お茶屋 (@ochayacco) 2016, 1月 11
デヴィッド・ボウイの逝去でBBCラジオではボウイの曲を繰り返し流していますが、このあと日本時間22時より追悼番組「Thank You David Bowie」を放送。日本からも聴けますhttps://t.co/BzMkepNcSt pic.twitter.com/5jj2mLsxZU
— British Music in JP (@britishmusicjp) 2016, 1月 11
ちょっとだけ聴いてみた。BBCラジオの追悼番組。本人の声も聴けた。“from Tokyo”とか言っていた。う~ん、言葉がわかればねぇ。「スペース・オディティ」がかかっていた。
そして何度見直しても、史上最もかっこいいデヴィッド・ボウイは、映画『クリスチーネ・F』で「ステイション・トゥ・ステイション」を歌う姿に思えてならない。両性具有のしなやかで妖しく美しいロックンロールアニマル。 https://t.co/uz4qFcla4w
— ぼのぼの (@masato009) 2016, 1月 11
そう!実は『クリスチーネ・F』で初めてボウイを認識したのであった。それまでは写真や少女マンガで見ていたけれど、特にどうということはなくて、この映画でカッコいいと思ったのが始まりだった。
そして、映画『キャット・ピープル』の最後の歌で悩殺されたのだった。『イングロリアス・バスターズ』でも使われていて、タランティーノの選曲のうまさを誉めてやった。よしよし(いいこ、いいこ)。
ひょっとするとボウイの曲で一番好きかもしれないのが「キャット・ピープル」。映画用に作られたオリジナルも『レッツ・ダンス』に収められたダンスヴァージョンも、どちらも最高。 https://t.co/Po3EJu9Q3e https://t.co/iOpkoM5Jv4
— ぼのぼの (@masato009) 2016, 1月 11
それでレコード屋に飛び込んで2枚目のベストアルバムを買った。音楽の師匠に教えてもらいながら過去の曲をいろいろ聴いていると、なんか自分的にタイムリーに「レッツ・ダンス」が発表され、師匠に連れられシリアス・ムーンライトツアーへ。「レッツ・ダンス」にも好きな曲がいっぱいあるけど、一番好きなのが「モダンラブ」。数年後、カラックスが『汚れた血』で使っていて、選曲のうまさを誉めてやった。よしよし(いいこ、いいこ)
https://t.co/pUv7lIflj2
モダンラブ
— お茶屋 (@ochayacco) 2016, 1月 11
映画はもちろん『地球に落ちて来た男』だ。見てないのもずいぶんあるな~。スコセッシの『最後の誘惑』にもピラト役で出てたりする。でも、浮いてるのよね~。ボウイに限らず、ロックスタアが映画に出演すると主役でもない限り浮いちゃうのだ。しかし、『バスキア』のアンディ・ウォーホル役はウォーホル自身が浮いてるから(?)なんかピッタリだった。
『バスキア』(ジュリアン・シュナーベル,1996)でウォーホルを演じるデヴィッド・ボウイ pic.twitter.com/d42c9OYiqs
— 広中真悟 (@Shingo_Hironaka) 2016, 1月 11
この前の復帰作では、何と言ってもこれが名曲だった。
https://t.co/Rh2wJlvzjk
— ぼのぼの (@masato009) 2016, 1月 11
これもぼのぼのさんに同感だ。みんな好きじゃないかな、「ヴァレンタインズ・デイ」。銃乱射事件が背景にあるそうだけど。
Very sorry and sad to say it's true. I'll be offline for a while. Love to all. pic.twitter.com/Kh2fq3tf9m
— Duncan Jones (@ManMadeMoon) 2016, 1月 11
『月に囚われた男』『ミッション:8ミニッツ』のダンカン・ジョーンズ監督の父でもあった。彼が生まれたとき作った歌とかあるし、プロコフィエフの「ピーターと狼」を朗読したレコードもあった。「息子は大学で哲学を学んでるんだ」と嬉しそうにインタビューに答えたこともあった。ボウイがダンカン少年と『時計じかけのオレンジ』を鑑賞し、易しく解説したから私たちは『ミッション:8ミニッツ』のような素晴らしい作品に出会えたのかもしれない。
映画でボウイ役をやってもらうなら、ティルダ・スウィントンとネットで誰かが言っていたけれど、我々(って誰?)は、シャーロット・ランプリングにお願いしたい(爆)。(ゲイリー・オールドマンと気が合ったそうで、「ネクストデイ」のPVにも出演してくれてるね。好きな人同士が仲良しなのはとても嬉しい。)
ボウイは思ったとおり、生涯アーティスト、クリエイターだった。変容し続けたが、自身を含め物事を客観的に見つめるところに変わりはなかった。
次は何をやらかしてくれるのか?「★(ブラックスター)」の後も回顧展があるし、本も出すんじゃないかな?
ティン・マシーンはパスしてゴメン
1983年 Serious Moonlight Tour 京都府立体育館
1990年 Sound + Vision Tour 東京ドーム
1996年 The Outside Tour 広島厚生年金会館
2004年 A Reality Tour 大阪城ホール
L’epoche.com ←こちらのページ(下の方)に「70 年代ロックの歌詞を論理的に翻訳する試み」があって、ボウイの歌も訳されていて、笑えるし泣けるし、おすすめです。