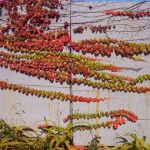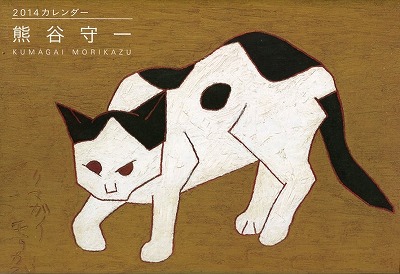2004年から2007年にかけて制作された「愛はとこしえ」シリーズは、モノクロームの線画だったので自分が教科書の端に描いた落書きを思い出したりした。もちろん、スケールも根の詰め具合も独創性も桁違い。へんてこりんなものが画面に隙間なく描出されている。そういう1枚1枚が更に壁いっぱいに並べられている。ある種の規則性(機械的な規則性じゃなくて有機的な規則性?)が生まれていて、部屋全体を見渡すとなんだか美しく見える。「天井にも床にも並べちゃえば~」などと思っていると、「チューリップに愛をこめて、永遠に祈る」でやられた(^_^;。入り口と出口のある白い部屋の内側が赤い水玉で四方八方おおわれて、これまた全体が赤い水玉の三つのチューリップが茎がねじれて咲いている。なんちゅう圧迫感。長時間いると気が狂いそうなので第一会場は早々に退散した。
つづく第二会場は、2009年に始まった「わが永遠の魂」シリーズがメインの展示で、「チューリップに愛をこめて、永遠に祈る」に匹敵するくらいの圧迫感があった。ネガフィルムのようなめったにない色の組合せを長時間見ていると脳髄が麻痺しそうな感じがした。エネルギーのマグマが四方からのしかかってくるようで、ここも早々に退散し、最後の展示「魂の灯」に並んだ。
並んでいると「注意書きをお読みください」と言われた。注意書きは、白線の内側から出ないように、また、怖くなったり気分が悪くなったりしたら内側からドアをノックするようにというような内容だった。ものすごく身構えてその白い立方体の中に入り、後ろでドアを閉められたと思ったら、宇宙が広がっていた!これぞ、「魂の灯」。これぞ、「永遠の永遠の永遠」。暗いガラス張りの部屋は無限に広く、水玉は電球に変換されて静かに色を変えながら灯りつづける。血行がよくなり体中に酸素が行き渡り、平静にはるか彼方の地平線まで見晴るかすような心持ちがした。こんなとき、芸術は心身の健康によいと心から思う。
売店で商品となった草間彌生グッズを見ると、「わが永遠の魂」に感じた圧迫感もなければ、「魂の灯」のような心洗われるような力もなかった。ユニークであることの面白さや楽しさを感じるだけだ。
『天使の分け前』上映会のとき撮った写真や、うえの写真のとおり、美術館全体を草間ワールドとしているのは良い試みだと思った。何より楽しい。導入部は楽しく、ちょっとかじると消化不良、しかし、最後はすっきりと。なかなか良い展覧会だったと思う。
(2013/12/01 高知県立美術館)