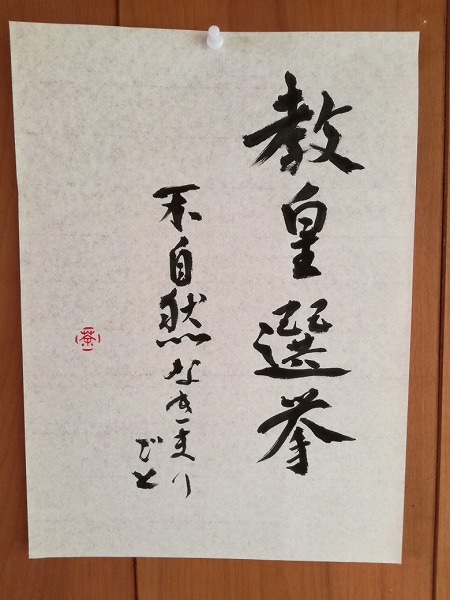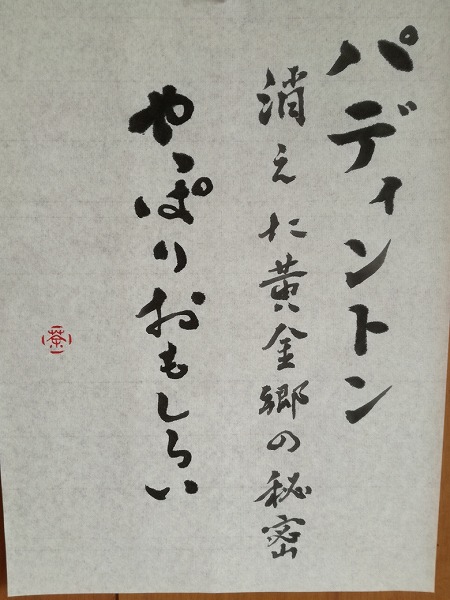新しいスマートフォンでもLINEを使えるように引っ越しをした。LINEの公式ページ「あんぜん引き継ぎガイド」のとおりやっても出来なかったが、どうにかこうにか出来たことをメモ。
[前提条件]
端末のOSは新旧ともにAndroid。
旧い端末ではSMS(ショートメッセージサービス)が利用できるデータ通信のみの契約で、通話ができる電話番号はなし。
新しい端末では通話も(SMSもデータ通信も)出来る契約で、新しい電話番号を取得。
旧い端末は手元にあり。
[成功]
新しい端末でLINEを起動し、「ログイン」タップ→「その他の方法でログイン」タップ→「電話番号でログイン」タップ→旧い端末のSMS電話番号を入力→旧い端末のSMSに送られてきた認証番号を新しい端末のLINEに入力→自分のアカウントが表示され引き継ぎ終了
[重要事項]
1 古い端末が手元にないと引き継ぎはできなかったと思われる。
2 新旧の端末で電話番号が同じであれば、古い端末が手元になくても引き継ぎはできる。
3 次の失敗1のとおり、QRコードが読み取れないことがある。
4 [追記]へ
[失敗1]
LINE公式サイトの「あんぜん引き継ぎガイド」の「AndroidからAndroidへ」を選択し、「以前の端末がある」の移行手順のとおりやってみた。以前の端末でQRコードを表示したが、それを新しい端末でどうやっても読み取れず断念。(新しい端末redmi14cの問題か?)
[失敗2]
「以前の端末がない」の手順どおりやってみた。新しい端末でその端末の電話番号を入力し、その端末のSMSに送られてきた認証番号をLINEに入力。すると縁もゆかりもない人のアカウントが表示された。「自分の情報で間違いない場合のみ、『はい、私のアカウントです』を選んで次に進んでください。」とあるので、「いいえ、違います」からは次に進めず行き詰まった。(新しい端末の電話番号は初めて手にするものだから、以前のLINEアカウントに紐付けられた電話番号とは異なるわけで、自分のアカウントが表示される道理はないと思いながらやってみたことだった。)
[ありがとう]
長年、愛用してきたHUAWEI P9 liteは、本当にすぐれものだった。電池の持ちがよく、写真の色が美しかった。他にもいろいろ使い勝手がよかった。検索したら2016年6月発売、2020年12月末でサポート終了だった。
[追記]
失敗2のとおり、誰かが使っていた電話番号を自分が使うことになったということは、いままで自分が使っていたSMSの電話番号も解約後は他の誰かが使うことになる。ということは、LINEアカウントに紐付けされている旧い電話番号を新しく取得した電話番号に変更しておくべきなのでは?変更できるのだろうかと思い検索した。その結果、LINEの「設定」→「アカウント」→「電話番号」で無事、変更できた。
LINEでは一つの電話番号にアカウントは一つしか登録できないようなので、当の電話番号でLINEをしていた人のアカウントは使用できなくなったことと思う。
検索していて面白い記事もあった。新しい電話番号に知らない相手からしょっちゅうかかってくるので着信拒否していたが、1日に平均4、5件のところ10件以上もかかってきて、試しに出てみたら数名の金融業者だったため、携帯の契約先に言って番号を変更してもらったとのこと。
携帯の電話番号が足りなくなっていることは、何年も前に聞いたことがあったが、この記事を読んで小説ができそうと思った。