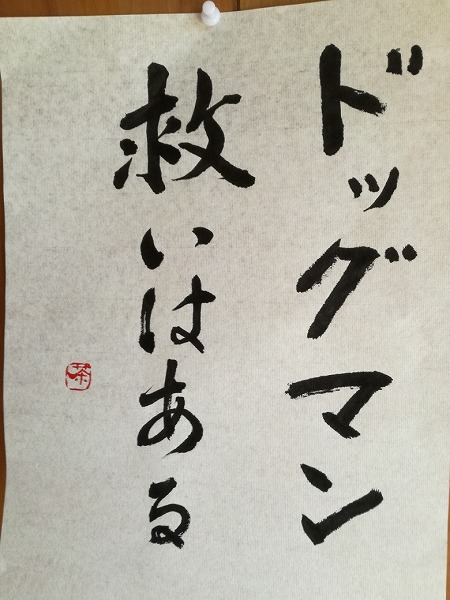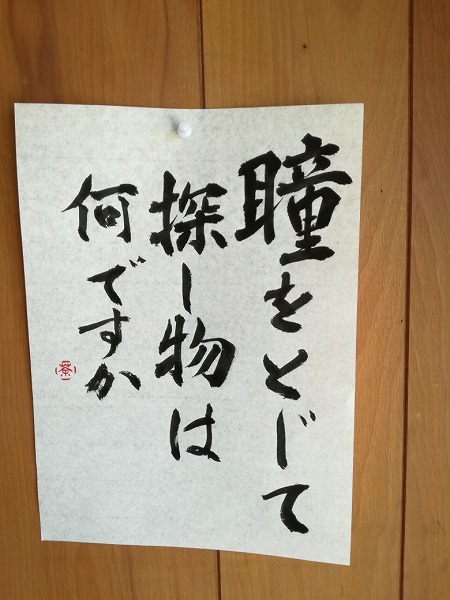好きには違いないが、なぜか好きとは言い切れない岡田くん。微妙に好きな岡田将生くんが出演した作品を観て暑気払いを行った。挙げ句の果てにインスタグラムまでフォローしたので、これは好き♥になったと言うべきだろうか。何か抵抗のようなものがあるけれど。
たくさん観た中で、もう一度観たいお気に入りをピックアップ。
【主演映画】
ゆとりですがなにか インターナショナル(2023)
セクハラ・パワハラ、日本で働く外国人、ネット通販などなど、時事ネタ満載、かつ、夫婦や家族の話になっている傑作コメディ。松坂桃李、柳楽優弥、安藤サクラ、仲野太賀ほか、役者がそろっている。
重力ピエロ(2009)
これも家族の話。兄が弟を受けとめる。感動したので感想を書いた。
僕の初恋をキミに捧ぐ(2009)
こっぱずかしいタイトルに尻込みしていたが、ドはまり。乙女心は不滅だ。心臓を移植しなければ限られた命の少年を岡田くんが、その初恋の彼女を井上真央ちゃんが演じる。二人とも可愛い。臓器移植について「そうかもなぁ、そうだろうなぁ」と思うところあり。明るくカラッと笑える(微笑ましい)好きな作品だが、30分短縮してもらえれば完璧。
アントキノイノチ(2011)
これも30分短縮してほしい。観てないと思っていたが、終盤の海辺の場面にきて観てたかもと思い、検索してみたら感想まで書いていた。観覧車の場面では、私なら「お元気ですか~(by井上陽水)」と声を掛けると思いながら観ていたが、上記リンク先のコメント欄にまったく同じことを書いていたので自分の変わりなさに驚いた。松坂桃李、染谷将太、仲野太賀が同じクラスの高校生役。この作品は「カタログ将生」と言ってもいいくらい黒将生、白将生、灰将生、コメディ将生の表情がうかがえる。
【脇役映画】
ドライブ・マイ・カー(2021)
もう一度観るには長尺だけれど、劇中劇「ワーニャ伯父さん」のラストシーンはやっぱり感動的だと思う。それに車中での岡田くんの演技は値千金。感想も書いているけど、車中の演技については西島秀俊のことのみ。なぜ!?(西島くんのファンだから、ひいき目なのかも。)
悪人(2010)
動画配信で再見。やはりもの凄く力のある作品だ。記憶にある場面がいくつもあった。ラストショットは灯台の元から夕焼けを見つめている二人(深津絵里と妻夫木聡)のそれぞれのアップで、二人の逃避行は悲しいだけではなく(生きるうえで必要な)美しいものであったんだと思わされ、思い出しても涙がでそうになる。でも、このカット、すっかり忘れていた。苦しくなる作品という思いを刷新してくれたので、再見してよかった。力のある作品は、素晴らしい鑑賞文を生む。間借り人の映画日誌の『悪人』のページと、そのリンク先(推薦テクスト)のページも素晴らしい。
天然コケッコー(2007)
動画配信にて再見。原作漫画は未読だが、各エピソードの余韻が、くらもちふさこ作品特有の「間」を彷彿させる。主人公(夏帆)たちが9年間すごした学び舎を卒業するときの郷愁がたまらない。島根県の田舎の、のどかさも方言もよい。
星の子(2020)
感想。
【連続ドラマ】
昭和元禄落語心中(2018)
レンタルDVDにて再見。全10話。物語がむちゃくちゃ面白い。名人、八代目有楽亭八雲(岡田将生)が幼少期(子役)から老年期までの大河浪漫。菊比古(岡田)、助六(山崎育三郎)、みよ吉(大政絢)、そして落語の四角関係が一つの見所だ。もう一つの見所は、元ヤクザで八代目に入門した与太郎(竜星涼)と、助六とみよ吉の忘れ形見の小夏(成海璃子)の落語好き具合で、ドラマ全体が落語賛歌になっている。芸能の中で最も厳しい芸が落語だと思っている私としては、描かれている厳しさが想像していたとおりで、それほど詳しくないのに当たっていたことが嬉しかった。原作もアニメも未見なので見当違いの意見かもしれないが、八代目は名人としては少々険しすぎかなと思った。晩年の力の抜け具合はよかったかな。噺家は50代からが本番だ。若手の力みは疲れる(^_^;。
大豆田とわ子と三人の元夫(2021)
全10話。主役の松たか子に魅せられる。その親友役の市川実日子もいい。人との繋がりを描いたコメディだけど、大好きな人との永遠の別れが織り込まれ忘れがたいドラマとなっている。
ザ・トラベルナース(2022)
全8話。中井貴一にハズレなし。短期の雇われ看護師(トラベルナース)が二人、同じ病院にやってくる。仕事はできるが思いやりがない看護師(岡田将生)が、ベテラン看護師(中井貴一)の影響で一人前になっていくバディもの。毎回、ゲスト出演の患者もいいキャラクターで涙あり笑いあり。特に第7話は、癌が転移した若い患者が「ゾンビは生きている」という映画を撮るのをサポートする話で、感動して2回観た。ベテラン看護師の秘密が徐々に明らかになっていくのも毎回楽しかった。
ゆとりですがなにか(2016)
全10話。正和(岡田将生)、山路(松坂桃李)、まりぶ(柳楽優弥)、茜(安藤サクラ)、山岸(仲野太賀)などのキャラクターが立ちまくりで可笑しい。主に仕事についてのドラマになっている。まりぶ、いいよ~(^o^)。まりぶ、好きだな~(^Q^)。
【ベストキャラクター】
『ゆとりですがなにか インターナショナル』「ゆとりですがなにか」の坂間正和さん、大好き♥。彼が一番好きなキャラクターだけど、あえてここは『1秒先の彼』のハジメ君をベストキャラクターにしたい。どちらもチャーミングなキャラだが、正和くんが好青年なのに対してハジメ君はイケズ(笑)。イケズなのに可愛い。岡田くんの演技としては険しいところも鋭いところも全くなくて“ゆるキャラ”なのだが、1秒先を行く彼なのでシャキシャキ小気味よい。
ここまで書いて、これは客観的には「大好きなんじゃないの」と思う。なお承服しがたいが(ぶつぶつ)。
よい俳優の条件は、何を着ても似合い、台詞のないときの表情が魅力的であることだと思っている。岡田くんはモデルなみに何を着ても似合う。汚い格好をした役を観たことがないので、汚い格好が似合うかどうか観てみたい。ちなみに『想いのこし』で女装してポールダンサーをしていたが、これは似合ってなかった(顔も身体も男らしいので女性には見えなかった)。菊比古役で高座にすわり女性を演じたときの方が女らしかった。台詞のないときの表情は美男美女が有利ではあるけれど、美男美女であれば魅力的だというわけではない。岡田くんの場合、憂いと表情筋の繊細な動き(と派手な動きの破顔、あと照明さんのおかげ)によって見飽きることがなく、たたずまいも役によって異なり、やっぱりよい俳優だと思う。