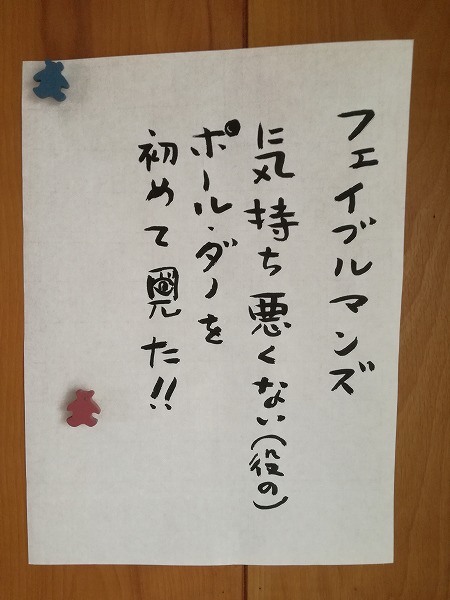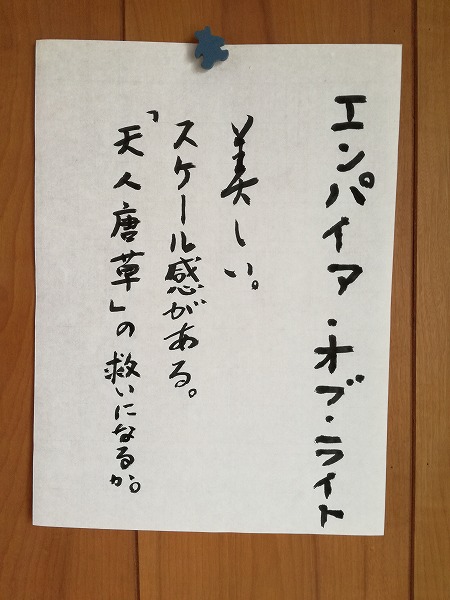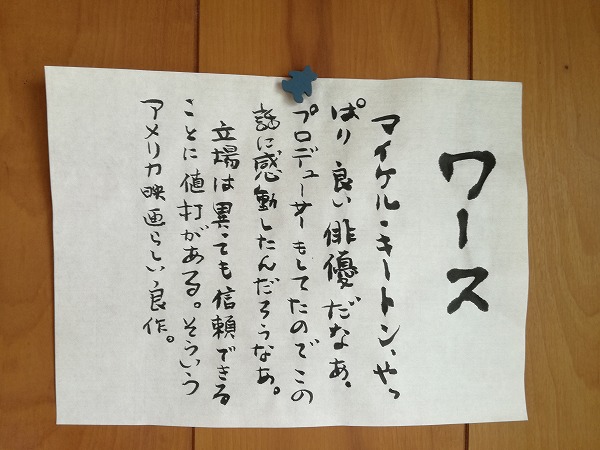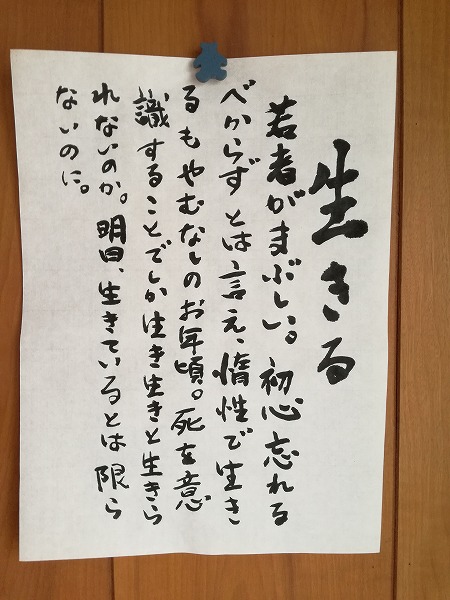
唯一知っているスクリーンサイズのスタンダードとオープニングの色調が時代を感じさせてくれる。丁寧に作られた作品だ。オリジナルに対するリスペクトも感じさせられる。黒澤明監督の『生きる』が若干上から目線な(?)圧があったのに対して優しい作品で、しかもビル・ナイ様が主演なのでとても好みだ。ビル・ナイ様が演じる課長さん(?)は、早くに妻を亡くし息子との意思疎通も控えめで内に悲しみを秘めているような感じだけれど、どこか可愛らしさとユーモアもある抑制の効いた(私の持っているイメージの)イギリス人らしいイギリス人でグッドなのだ(課長さんはスコットランド出身だそうだけど)。「ゴンドラの唄」は出てこないけれど、スコットランドの民謡「ナナカマドの木」が、公園で遊ぶ子どもたちのラストシーンにピッタリで名翻案だと思った。
もうこの年になると(あるいは色んな生き方があると多少知るようになると)、別に生き生きと生きられなくてもいいと思う。自分自身では、あまり欲がないから幸せだという気がする。ゾンビでも最期にがんばってちいさな満足感を得た課長さん、幸せだったよね。
(2023/04/15 TOHOシネマズ高知3)