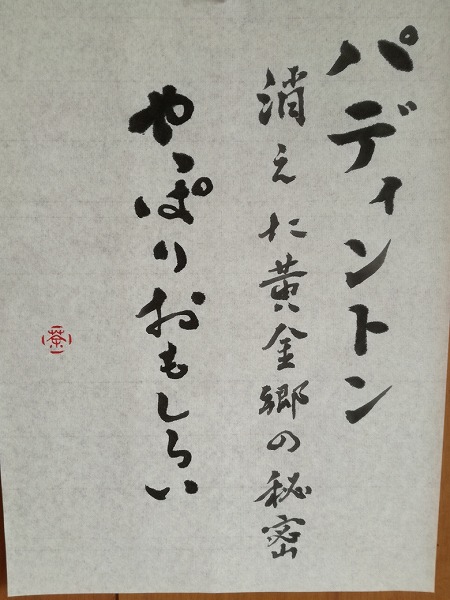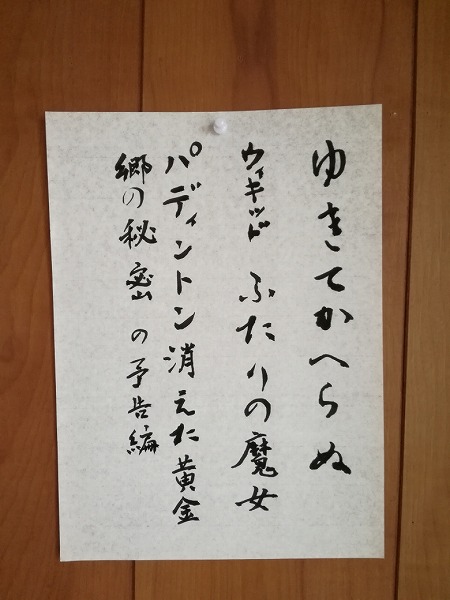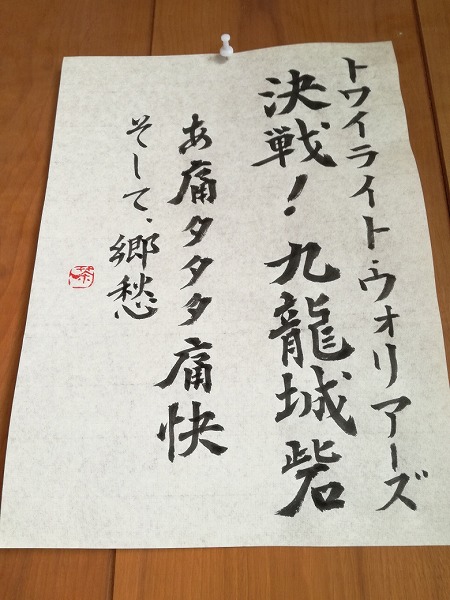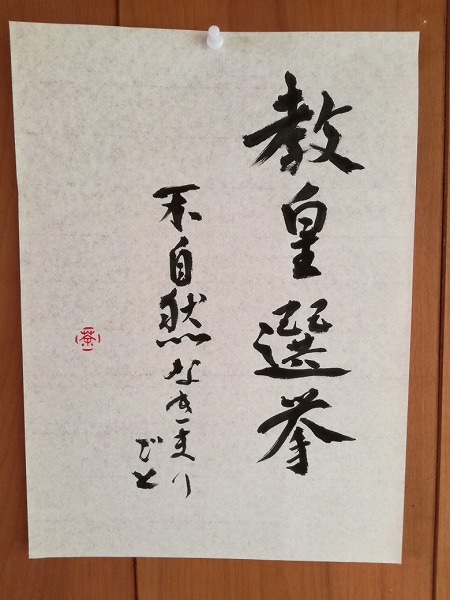
最後にローレンス(レイフ・ファインズ)が、亀を両手で持って水に返すのは何を意味しているのだろう?灰は灰に塵は塵に亀は池に?人は土に還り、生きている亀は水辺に。それが自然というものだから?
この映画を観に行く直前に占い師をしている友だちから、タロットカードからのメッセージだとして「不自然なきまりごとを設けて、自然に起こることを入ってこないようにしていませんか。地図に載っていないものの中へリラックスしていきましょう。すべてを上手くやろうとしなくて良いのです。」とLINEをもらった。ちんぷんかんぷんだったが、選ばれた新教皇をローレンスが認めたところで、「このことだったのかー!」と思った。タロットカードからのメッセージは、私へというよりローレンスへのメッセージとすれば大変しっくりくる。
女性は教皇(枢機卿)になれないため、スイスで女性の臓器を取り除きバチカンに入ろうとしたが翻意し、自然体でバチカンに入ったベニテス(カルロス・ディエス)。それを知りながらコンクラーベで選ばれたベニテスを教皇と認めるローレンス。それでこそ前教皇の一番弟子というものだ。これまでのカトリックの地図には載っていない世界へ踏み出したと思う。すべてが上手くいかなくても善き方向へ行くのではないか。保守派、改革派、おとし穴といろいろあったコンクラーベだが、大穴中の大穴にして理想のキリスト教徒らしいベニテスに未来を託した他の枢機卿たちの善意にも希望を感じる。創作物は社会をリードすることがあるので、そういう意味でもよい作品だと思う。
修道女を演じていたのはイザベラ・ロッセリーニだったのか。すごい存在感だった。
(2025/05/09 TOHOシネマズ高知2)