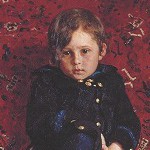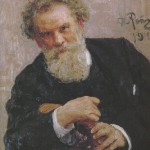先週、大阪で命の洗濯をしてきた。すぐ汚れるので、できたら1日置きに洗濯したい。残念ながら、そうもいかないので反芻あるのみ。
まずはホールがよかった。2008年の「マラーホフの贈り物」もフェスティバルホールで観たが、その後、建て直された。前のホールは何だか圧迫感があって舞台も遠く感じたが、新しいホールは開放感があり、座席も前の人の間に後ろの人の席というふうに配置され、とても観やすい。舞台も近く感じた。それに大阪の女性観客はおしゃれで、夜の公演にふさわしくアクセサリーやお洋服がキラキラしていて私の気分を盛り上げてくれた。
公演はプログラムもダンサーもよくて、おしまいには思わず席を立って拍手していた。これまで前の人が立ちあがり見えなくなったので立ち上がるということは何度かあったが、自発的スタンディングオベイションは初めてだ。やっぱり、「最後のアクション超大作」とか「ファイナル」というのに弱いらしい(笑)。
Cプロ
「白鳥の湖」第二幕より
(振付:レフ・イワーノフ/音楽:チャイコフスキー/オリガ・スミルノワ、ウラジーミル・マラーホフ、東京バレエ団)
オデット役のスミルノワちゃん、若いのに堂に入った踊りだ。でも、それよりも王子が~、素晴らしい。王子はサポートに徹してあまり踊らないんだけど、オデットに向ける視線や身体の傾け方で、このうえなく大切に思っていることが伝わってくる。マラーホフの「白鳥の湖」全幕は見られないのかなぁ。
「トゥー・タイムス・トゥー」
(振付:ラッセル・マリファント/音楽:アンディ・カウトン/ルシア・ラカッラ、マーロン・ディノ)
数年前のバレエ・フェスティバルでシルヴィ・ギエムが一人で踊った「トゥー」の二人バージョンだ。閃光が力強いリズムと金属音に合わせて暗闇と空間を切り取っていく。素早く弧を描く腕が、ライトが当たるところに触れると閃光のように見えるのだ。マーロン・ディノのパワフルな踊りが、音楽にも演出にもピッタリだった。
「椿姫」より第一幕のパ・ド・ドゥ
(振付:ジョン・ノイマイヤー/音楽:ショパン/マリア・アイシュヴァルト、マライン・ラドメーカー)
マルグリットを追いかけるアルマン。マルグリットは年上の余裕でいなしていたが、ついに根負けか(笑)。二人の演技力と、踊りで物語れる振付をしたノイマイヤーに敬服。
「海賊」より奴隷のパ・ド・ドゥ
(振付:マリウス・プティパ/音楽:コンスタンティン・フリードリヒ・ペーター/ヤーナ・サレンコ、ディヌ・タマズラカル)
出た、タマズラカル君(笑)。←なぜ、笑う(^m^)。この人、「ニーベルングの指環」(2005)の仰天キャラクターと「チャイコフスキー」(2011)
のそつなき王子の両方を踊れてしまう器用な人。どちらかというとキャラクターが向いているような気がする。今回は元気いっぱいで本当に楽しそうに踊っていた。太陽のタマズラカル君と月のサレンコちゃん。二人の温度差が見物だった。
「瀕死の白鳥」
(振付:マウロ・デ・キャンディア/音楽:サン=サーンス/ウラジーミル・マラーホフ)
雄の白鳥や~。トロカデロ・モンテカルロバレエ団のダンサーに掛かると笑いが取れそうな振付だ。(フォーキン版「瀕死の白鳥」を初めて観たのはトロカデロ・モンテカルロバレエで、そのときは笑ってしまった。後年、コミックじゃない方を観て、トロカデロ・ダンサーの踊りとあまり違わないのに驚いたことがある。)笑いが取れそうやなと思いながら、切なさに涙がにじんでくるという不思議な体験をした。この公演でもっとも感動した。
-休憩-
「ロミオとジュリエット」より第一幕のパ・ド・ドゥ
(振付:ジョン・クランコ/音楽:プロコフィエフ/マリア・アイシュヴァルト、マライン・ラドメーカー)
やっとヌレエフ版の呪縛から解放されたような気がする。クランコ版もいいなぁと思えるようになった。第一部で「椿姫」を踊ったアイシュヴァルトとラドメーカーが、十代の恋を初々しく踊る。特にジュリエットが、可愛いーーー!
「タランテラ」
(振付:ジョージ・バランシン/音楽:ルイス・モロー・ゴットシャルク/ヤーナ・サレンコ、ディヌ・タマズラカル)
出た、タマズラカル君(笑)。タンバリン、タンバリン(^o^)。ぴょんぴょん、くるくる~。
熱帯タマズラカル君と寒帯サレンコちゃん。二人の温度差が見物だった。
「ラ・ペリ」
(振付:ウラジーミル・マラーホフ/音楽:ヨハン・ブルグミュラー/吉岡美佳、ウラジーミル・マラーホフ)
マラーホフの衣装がスカート(?)だったので、はじめ女性かと思ってしまった。エジプトの王子と妖精のお話だそうだが、衣装になれる間もなく終わってしまう。全幕じゃないからね~。
この二人の踊りを観ていると、バレエってテクニックだけじゃないんだと改めて思う。吉岡さんがマラーホフのサポートを受けて、片足でゆっくりと回転する。この簡単な動きが本当に美しい。このとき、吉岡さんだけでなくマラーホフ込みで美しい。これが一体となると言うことなんだろう。
「椿姫」より第三幕のパ・ド・ドゥ
(振付:ジョン・ノイマイヤー/音楽:ショパン/ルシア・ラカッラ、マーロン・ディノ)
ノイマイヤー、すごいわ~。「椿姫」第三幕のパ・ド・ドゥといえば、18禁バレエ。世界バレエ・フェスティバルでジョエル・ブーローニュとアレクサンドル・リアブコの踊りを観たときも凄いと思ったけど、今回も圧巻だった。振付どおりに踊ったら物語になるものね~などと思いながら観ていたのが、いつの間にか引き込まれていた。拍手の嵐~。
「白鳥の湖」より”黒鳥のパ・ド・ドゥ”
(振付:レフ・イワーノフ/音楽:チャイコフスキー/オリガ・スミルノワ、セミョーン・チュージン)
黒鳥のパ・ド・ドゥは盛りあがる。32回転があるものね。チュージンさんは滞空時間が長かった。
「ヴォヤージュ」
(振付:レナート・ツァネラ/音楽:モーツァルト/ウラジーミル・マラーホフ)
マラーホフといえば「ヴォヤージュ」、「ヴォヤージュ」といえばマラーホフなんだそうである。今回は、全5公演、全てで「ヴォヤージュ」を踊るということだった。初めて観てなるほどと思った。マラーホフはクラシックもコンテンポラリーもOK、王子も踊ればキャラクターで笑わせたり泣かせたりできるし、ポワントを穿かせば女性ダンサーも顔負けなのだ(と噂に聞くばかりなのが残念なのだが)。そういう多才な彼が「ヴォヤージュ」を演じれば、その時々によって変幻自在に楽しませてくれるだろう。「ヴォヤージュ」は、パントマイムが加味された踊りなのだ。
旅から旅への旅ガラスだから、手を振る場面が何度かある。これまでどんなにして手を振っていたのだろう。今回は何だか、とても切なかった。
(2013/05/27 大阪フェスティバルホール)