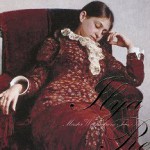映像がとても美しい。東京の風景をとても美しく切り取っていること、朝も夕も夜もやわらかな色合いに仕上げていること、カメラワークも凝っていること、スローモーションや音の付けたかなど、西川作品で初めて監督の存在を感じ、うまいなぁと唸った。
里子(松たか子)も貫也(阿部サダヲ)も瞳が黒々と静かに輝いていて、二人の姿形、動きを追っているだけで面白い映画だった。観て楽しむ分には西川監督の最高傑作だと思う。ただし、物語としては、あまり後に残らない感じがした。
里子としては、「自分以外の女性と寝れるのね、ああ、それなら、好きなだけ寝ればいいじゃないの」という怒りと、「何をぐだぐだやってんだか、あなたは魅力があるんだから、前を向いてたぶらかしてきなさい」と後ろ向きの夫に自信を取り戻してほしい思いと、「また店を持ちたい」と夫の夢を自分の夢として叶えたい気持ちがあったのではないかと思う。それで詐欺の提案をしたわけだが、「夢を売るのよ(相手のためにもなるのよ)」と罪悪感をごまかすのがうまい。
貫也が自分の掌で詐欺っているうちはよかったが、ひとみちゃん(江原由夏)あたりから、貫也自身が考えて行動するようになると、もう、貫也にとって自分はいらない存在ではないかと心配になって、ついにハローワークの職員(木村多江)のところへ乗り込んでしまったのだろう。
貫也の方は、咲月(田中麗奈)など始めの方はよかったが、詐欺という心身ともに疲弊するハードワークに、これは浮気の罰だと感じ始め爆発する。このとき里子は、夫と自分の夢を叶えるためにやってきたことが、夫に対する「復讐」だったと初めて自覚したのかもしれない。貫也に爆発されて、「あなたのためにやっているのに」と里子も言い返しかけたが、そういやそうかもと気がつくと、もう、そう思うなら思われてもいいわと口をつぐんだのではないだろうか。
この場面あたりから二人の心のすれ違いが顕著になって、これだけ意思疎通ができないでいると、いずれ別れるぞ、いつ別れるんだと思って観ていた。
詐欺という復讐により自分たちの夢を切り売りしたため、二人の夢はなくなり、一人の夢でもなくなるのではないか。
ところが、別れるどころか、里子は第1番目の浮気の相手(鈴木砂羽)に夫が借りたお金を妻として返済するのだ。(いろいろ解釈はあるだろうけど、私は「いちかわ」と書いた封筒で返済したのは里子だと思っている。)
しかも、ラストシーンでは、里子と貫也は別々のところにいるらしいのに、二人が同時に同じもの(かもめ)を見上げたような演出がほどこされているものだから、「作り手は二人の気持ちが通じているとでも言いたいのか?」という気持ちにさせられた。
そうなると、夫婦というものはわからんなぁという気持ちがのこり、考えてもわからんだろうから考えないことにして、物語としては後に残らない作品とあいなった。
監督:西川美和
(2012/09/19 TOHOシネマズ高知1)